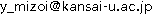
文化史(ドイツ語圏、英語圏、日本語圏を中心とする)が専門。単著に『動物園・その歴史と冒険』(中央公論新社、2021)、『水族館の文化史』(勉誠出版、2018)、『動物園の文化史』(勉誠出版、2014)、『ファウスト伝説』(文理閣、2009)がある。ほか編著『グリムと民間伝承』、共編著『想起する帝国: ナチス・ドイツ「記憶」の文化史』、共著『ドイツ奇人街道』など。
2025/05/31 更新

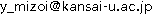
文化史(ドイツ語圏、英語圏、日本語圏を中心とする)が専門。単著に『動物園・その歴史と冒険』(中央公論新社、2021)、『水族館の文化史』(勉誠出版、2018)、『動物園の文化史』(勉誠出版、2014)、『ファウスト伝説』(文理閣、2009)がある。ほか編著『グリムと民間伝承』、共編著『想起する帝国: ナチス・ドイツ「記憶」の文化史』、共著『ドイツ奇人街道』など。
博士(文学) ( 2008年3月 )
その他 / その他 / 文化史(ドイツ語圏、英語圏、日本語圏を中心に)
人文・社会 / 文化人類学、民俗学
関西大学 文学研究科
- 2008年
関西大学 文学部 ドイツ語ドイツ文学科
- 2003年
Rise of Lost Worlds Part 4: Kokoro’s Robotic Animals in the Cultural History of Dinosaurs in Japan.
溝井裕一
関西大学文学論集 74 ( 3 ) 91 - 133 2024年12月
Rise of Lost Worlds. A Cultural History of the Dinosaur Park, Part 3: Walt Disney’s Creatures at the ‘Magic Skyway’ Ride.
溝井裕一
関西大学文学論集 73 ( 3 ) 135 - 170 2023年12月
Rise of Lost Worlds. A Cultural History of the Dinosaur Park, Part 2: Carl Hagenbeck’s Extinct Monsters.
溝井裕一
関西大学文学論集 72.4. 51-86 2023年3月
Rise of Lost Worlds. A Cultural History of the Dinosaur Park, Part 1: The Geological Exhibition at the Crystal Palace Park, Sydenham.(この論文(Rise of Lost Worlds第1部)は、『ヴィクトリア朝文化研究』第19号所収の「水晶宮の「ロスト・ワールド」:ヴィクトリア朝時代の古生物展示について」を加筆修正のうえ英訳したものである)
溝井裕一
関西大学『文学論集』第71巻第4号 73-107 2022年3月
水晶宮の「ロスト・ワールド」—ヴィクトリア朝時代の古生物展示について
溝井裕一
ヴィクトリア朝文化研究 179-208 2021年11月
The Exhibition of Oceans: A History of the ʻImmersive Exhibitionʼ at Public Aquariums from the 19th to the 21st Century
Mizoi Yuichi
關西大學文學論集 66 ( 3 ) 79 - 122 2016年12月
「魚を横から,下から見ること」の文化史 : ローマ式養魚池から博物誌,ヴンダーカンマー,金魚鉢,水族館まで
溝井 裕一
關西大學文學論集 65 ( 3 ) 77 - 113 2016年3月
「『ハーメルンの笛吹き男伝説』における父親像と母親像」(野口芳子編『グリム童話とドイツ伝承文学における父親像と母親像』) 査読
溝井裕一
日本独文学会研究叢書 3-14頁 2014年10月
〈ジュラシック・パーク〉へいたる道 : 近世-近代ヨーロッパの動物園とその背景にある自然観について
溝井 裕一
關西大學文學論集 62 ( 2 ) 61 - 85 2012年9月
動物園のルーツを探る : 古代から中世までの「動物コレクション」とその役割について
溝井 裕一
關西大學文學論集 62 ( 1 ) 25 - 54 2012年7月
「動物王カール・ハーゲンベック」の神話と日本人
溝井 裕一
ドイツ文学論攷 ( 54 ) 7 - 30 2012年
グリーンマンと中世の森
溝井 裕一
説話・伝承学 19 195 - 212 2011年3月
「『野獣の主』伝承とヨーロッパの狩猟文化―ドイツ語圏を中心に」 査読
溝井裕一
『昔話―研究と資料』 第39号 166-182 2011年3月
伝説と集合的記憶 : 伝説において過去はいかに「想起」されるのか
溝井 裕一
関西大学東西学術研究所紀要 42 A61 - A100 2009年4月
伝説は語る : 伝説研究に何ができるのか-その意義と展望について
溝井 裕一
独逸文学 51 213 - 237 2007年
「ファウスト博士の変身と古代自然観-16世紀民衆本における『変身魔術』をめぐる考察」 査読
溝井裕一
『昔話―研究と資料』 第34号116-129頁 2006年7月
「飲み込む龍」と通過儀礼 : ヨーロッパの図像における「死と再生」の概念について
溝井 裕一
関西大学東西学術研究所紀要 39 79 - 103 2006年4月
樹木文化のなかのヨーロッパ船舶史 : ヨーロッパにおける樹木観の変容と、船舶建造にともなう森林破壊をめぐる考察
溝井 裕一
千里山文学論集 75 133 - 159 2006年3月
„Der Klabautermann- und der Funadama-Glauben - Zu Schutzgeistern der Schiffe in Nordeuropa und in Japan“
MIZOI,Yuichi
『独逸文学』 第50号179-203頁 ( 50 ) 179 - 203 2006年3月
魔術師ファウストの「死と再生」について--『実伝ヨーハン・ファウスト博士』と伝説の比較研究
溝井 裕一
ドイツ文学論攷 ( 48 ) 27 - 47[含 独語文要旨] 2006年
「『魔女』に対する拷問と処刑」(シンポジウム「グリム・メルヒェンと『魔女』報告」)
溝井裕一
『独逸文学』 第49号269-283頁 ( 49 ) 219 - 283 2005年3月
増補新版 水族館の文化史ー幻蒼世界の過去と未来 (中公選書 157)
溝井 裕一( 担当: 単著)
中央公論新社 2025年3月 ( ISBN:4121101596 )
Sea Currents in Nineteenth-Century Art Science and Culture (edited by Kathleen Davidson & Molly Duggins).
溝井裕一( 担当: 分担執筆 範囲: 191-207 (11. Aquariums under the Rising Sun: A Cultural History of Early Public Aquariums in Japan, 1882-1903). 本章は勉誠出版の許諾を得て、拙著『水族館の文化史』の第3章の一部を翻訳・修正のうえ掲載したものである。)
Bloomsbury 2023年 ( ISBN:9781501352782 )
恐竜、帝国に出現すー植民地時代の「ジュラシック・パーク」
溝井裕一( 担当: 単著)
ゲンロン 2022年10月
動物園・水族館と「肉食」―歴史でたどる「見ること」と「食べること」のかかわり
溝井裕一( 担当: 単著)
現代思想2022年6月号 特集=肉食主義を考える 2022年6月
動物園・水族館と戦争―その複雑な関係
溝井裕一( 担当: 単著)
博物館研究 2021年7月
『動物園・その歴史と冒険』
溝井裕一( 担当: 単著)
中央公論新社 2021年
コロナ禍中の動物園
溝井裕一( 担当: 単著)
アステイオン 第93巻 2020年11月
SS先史遺産研究所アーネンエルベーナチスのアーリア帝国構想と狂気の学術
Kater, Michael H., 森, 貴史, 北原, 博, 溝井, 裕一, 横道, 誠, 船津, 景子, 福永, 耕人( 担当: 共訳)
ヒカルランド 2020年2月 ( ISBN:9784864718271 )
「水族館 その歴史的な歩み」(錦織一臣編『大人のための水族館ガイド』)
溝井 裕一( 担当: 分担執筆)
養賢堂 2018年11月
水族館の文化史―ひと・動物・モノがおりなす魔術的世界(サントリー学芸賞受賞)
溝井裕一( 担当: 単著)
勉誠出版 2018年6月
A Cultural History of Watching Fish ‘From the Side and from Below’: Roman Fish Ponds, Natural History Books, Cabinets of Curiosity, Goldfish Bowls and Aquariums. (長谷部剛編『日本言語文化の「転化」』)なお本稿は溝井裕一著「『魚を横から,下から見ること』の文化史 ─ローマ式養魚池から博物誌,ヴンダーカンマー, 金魚鉢,水族館まで」(関西大学文学論集 65.3/4 (2016) 77–113)を加筆修正のうえ英訳したものである。
MIZOI,Yuichi( 担当: 分担執筆)
関西大学東西学術研究所 2017年3月
「怪物のうごめく海で―古代~中世ヨーロッパにおける『ひとと水族の 関係史』」大野寿子編『グリム童話と表層文化』
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
勉誠出版 2017年
想起する帝国ーナチス・ドイツ「記憶」の文化史
溝井 裕一, 細川 裕史, 齊藤 公輔( 担当: 共編者(共編著者))
勉誠出版 2016年12月 ( ISBN:4585221557 )
「人狼伝説から人狼裁判へ」(浜本隆志編『欧米社会の集団妄想とカルト症候群――少年十字軍、千年王国、魔女狩り、KKK、人種主義の生成と連鎖』)
溝井 裕一( 担当: 分担執筆)
明石書店 2015年9月 ( ISBN:4750342432 )
「メルヒェンと伝説、その驚きの世界観-変身譚を中心に」(大野寿子編『グリムへの扉』)
溝井 裕一( 担当: 分担執筆)
勉誠出版 2015年5月
「シュトゥットガルト―産業都市がもつ『ワイルド』な側面に迫る」(森貴史編『ドイツ王侯コレクションの文化史』)
溝井 裕一( 担当: 分担執筆)
勉誠出版 2015年1月
ドイツ奇人街道
森 貴史, 細川 裕史, 溝井 裕一, 小路 啓之, カバーイラスト( 担当: 共著)
関西大学出版部 2014年7月 ( ISBN:4873545862 )
動物園の文化史―ひとと動物の5000年
溝井裕一( 担当: 単著)
勉誠出版 2014年4月 ( ISBN:4585220828 )
グリムと民間伝承ー東西民話研究の地平
溝井裕一( 担当: 編集)
2013年7月 ( ISBN:9784905383031 )
「『笛吹き男』伝説の舞台、ハーメルンを歩く」ほか(5、6、9章) (浜本隆志ほか編 『現代ドイツを知るための62章』)
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
明石書店 2013年4月
「日本昔話研究者としてのフリッツ・ルンプ」 (山本登朗編 『日本を愛したドイツ人 フリッツ・ルンプと伊勢物語版本』)
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
関西大学出版部 2013年3月
「ドイツの民間伝承における異界と異人」 (大野寿子編 『超域する異界』)
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
勉誠出版 2013年1月
「『境界の顔』としてのグリーンマン」 (蜷川順子編 『顔をみること』)
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
関西大学出版部 2012年3月
ヨーロッパ・ジェンダー文化論 (女神信仰・社会風俗・結婚観の軌跡)
浜本 隆志, 伊藤 誠宏, 柏木 治, 森 貴史, 溝井 裕一( 担当: 共著)
明石書店 2011年4月 ( ISBN:4750333689 )
「聖ヨハネ祭と『ハーメルンの笛吹き男伝説』」 (浜本隆志編 『異界が口を開けるとき』)
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
関西大学出版部 2010年3月
ファウスト伝説―悪魔と魔法の西洋文化史
溝井 裕一( 担当: 単著)
文理閣 2009年8月 ( ISBN:4892595985 )
「グリーンマン探訪」 (浜本隆志編 『ヨーロッパ人相学』) 査読
溝井裕一( 担当: 分担執筆)
白水社 2008年7月
ファウスト伝説ー近代における「魔法使い」像の形成と変容
溝井, 裕一
溝井裕一 2008年
建築知識2024年6月号 建物種類ごと歴史図鑑
溝井裕一( 担当: 監修 範囲: 水族館ー小規模施設から本来の生態を伝える展示に(58-69ページ))
エクスナレッジ 2024年5月
観察の変遷「ヒキ」でたどる(信岡朝子著『快楽としての動物保護』)
溝井裕一( 担当: 単著)
日本経済新聞 2020年11月
随想(神戸新聞) 8回にわたりコラム掲載(ロンドンの豪雨、水族館と「没入感」、「海底散歩」を楽しんだ明治期の人びと、幻の阪神パーク水族館、神戸・大阪の「テーマ・アクアリウム」、ルートヴィヒ2世の奇城、ヘック兄弟の絶滅動物復元計画、原生林・動物の幻影を追って)
溝井裕一
神戸新聞 夕刊 2019年5月
【木下直之著『動物園巡礼』書評】動物園―いのちと向き合う現場 ひとと動物たちの泥臭い物語
溝井裕一
週刊読書人 2019年3月
「ファウストはなぜモテる?!」
溝井裕一( 担当: 単著)
『幕があがる。』まつもと市民芸術館 2012年10月
「アクチュアルに、文化と歴史から読み解く好著」 (浜本隆志ほか編著『ドイツのマイノリティ』について)
溝井裕一( 担当: 単著)
『書評』 2010年10月
「1608年の『伊勢物語』とその17世紀日本における版本挿絵への影響」 (山本登朗編 『日本を愛したドイツ人 フリッツ・ルンプと伊勢物語版本』)
溝井裕一, 山本登朗
関西大学出版部 3-73頁 2013年3月
「魔術師ファウスト―悪魔と旅するドイツ」
溝井裕一
2009年12月
[シンポジウム報告] 「文化的記憶」とメディアとしての文学
酒井 友里, 齊藤 公輔, 溝井 裕一, 今本 幸平
独逸文学 51 283 - 286 2007年3月
異界が口を開けるとき--「ハーメルンの笛吹き男伝説」と夏至にまつわる民間信仰について
溝井 裕一
ドイツ文学 6 ( 1 ) 216 - 218 2007年
3.集合的記憶のメディアとしての文学(「文化的記憶」とメディアとしての文学)
溝井 裕一
独逸文学 51 284 - 285 2007年
異界が口を開けるとき:「ハーメルンの笛吹き男伝説」と夏至にまつわる民間信仰について
溝井 裕一
ドイツ文学 133 ( 0 ) 209 - 218 2007年
3.よみがえるファウスト : ファウスト民衆本にみられる、前キリスト教的世界観について(2004年度修士論文要旨)
溝井 裕一
独逸文学 50 236 - 239 2006年3月
2004年度修士論文要旨
細川 裕史, 森本 真理子, 溝井 裕一
独逸文学 50 233 - 239 2006年3月
タンホイザーとゲルマン信仰 : 「地獄の女神ヴィーナス」の素顔
溝井 裕一
独逸文学 49 373 - 382 2005年3月
『タンホイザー』を巡る3つの視点
今本 幸平, 細川 裕史, 溝井 裕一
独逸文学 49 355 - 355 2005年3月
溝井 裕一
独逸文学 49 269 - 283 2005年3月
ファウスト伝説の起源 : 1587年のファウスト民衆本と魔術の歴史との関係について (二宮まや教授古稀退職記念号)
溝井 裕一
独逸文学 48 143 - 168 2004年
ファウスト伝説の起源--1587年のファウスト民衆本と魔術の歴史との関係について
溝井 裕一
独逸文学 ( 48 ) 166 - 168 2004年
ヨーロッパの水族館―その過去と未来 招待
溝井裕一
第10回水族館シンポジウム「水族館とは?日本の水族館を考える」 2023年12月
ヨーゼフ・パレンベルクの実物大恐竜彫刻と英米独の自然史博物館
溝井裕一
日本独文学会春季研究発表会 2025年5月
水槽のなかに広がる宇宙ー水族館の誕生・発展とその文化的背景について 招待
溝井裕一
日本箱庭療法学会第 35 回大会 2022年10月
帝都に響きわたる咆哮―近代ヨーロッパの動物園・水族館文化 招待
溝井裕一
日本ヴィクトリア朝文化研究学会 2020年11月
水族館の文化史―歴史をとおして考えるその過去と未来 招待
溝井裕一
北海道大学学芸員リカレント教育プログラム 2020年2月
水族館の文化史―展示とともに歩む人と魚の物語 招待
溝井裕一
説話・伝承学会 2019年度春季大会 2019年4月
「想起された「ゲルマン的自然」―古代生物復元計画」(ポスター発表、溝井裕一、細川裕史、齊藤公輔「想起する帝国―ナチス・ドイツにおける「集合的記憶」に関する考察」)
溝井 裕一
日本独文学会 2014年10月
「ハーメルンの笛吹き男伝説の場合」(野口芳子ほか シンポジウム≪グリム童話とドイツ伝承文学における父親像と母親像≫)
溝井裕一
日本独文学会 2013年9月
「グリーンマンと探検する森の国ドイツ」
溝井裕一
Klub Zukunft 2013年2月
「『解雇された兵隊』と近世の家父長制」 (野口芳子、ベルンハルト・ラウアーほか グリム童話刊行 200 年記念 シンポジウム. ≪グリム童話とジェンダー ―文字・図像・音楽にみる家族像―≫)
溝井裕一
2012年10月
「メルヒェンの世界観・伝説の世界観―変身譚を中心に」 (大野寿子、ベルンハルト・ラウアーほか 東洋大学創立125周年事業『グリム童話』刊行200年記念国際シンポジウム「グリム童話200年のあゆみ―日本とドイツの架け橋として―」)
溝井裕一
2012年10月
「近代ドイツ動物園の興亡―帝国主義から生態系改造計画まで」
溝井裕一
阪神ドイツ文学会 2012年7月
「ドイツの民間伝承における異界と異人―ハーメルンの笛吹き男からメフィストフェレスまで」 (大野寿子ほか シンポジウム(研究発表会)総合テーマ:「異界」へのいざない―ドイツ、日本、中国の文学・音楽から)
溝井裕一
2011年6月
「魔法使いファウスト伝説と西洋文化史」
溝井裕一
Klub Zukunft 2010年10月
「悪魔が奏でる音の魔力-笛吹き男・ファウスト・死の舞踏」
溝井裕一
東西学術研究所 第六回研究例会 2009年1月
「ファウスト伝説―近代における『魔法使い』像の形成と変容」
溝井裕一
グリムと民間伝承研究会 2008年6月
「魔女擁護者レルヒアイマーと『悪魔伝説』-『魔法に関するキリスト教的考察と警告』にみる16世紀の世界観」
溝井裕一
日本独文学会 2008年6月
「聖ヨハネ祭と『ハーメルンの笛吹き男』伝説」
溝井裕一
東西学術研究所、平成19年度第五回研究会 2007年12月
「異界が口を開けるとき-ハーメルンの笛吹き男伝説にみる夏至にまつわる世界観」
溝井裕一
歌謡研究会・比較民話研究会合同例会 2007年12月
「集合的記憶のメディアとしての文学」(シンポジウム《文化的記憶のメディアとしての文学》)
溝井裕一
関西大学独逸文学会 2006年9月
「異界が口をあけるとき-ハーメルンの笛吹き男伝説にみる夏至にまつわる世界観」
溝井裕一
日本独文学会 2006年6月
「クラバウターマン信仰と日本の船霊-船に宿る守護霊をめぐる考察」
溝井裕一
歌謡研究会・比較民話研究会合同例会 2005年12月
「魔術師ファウストの変身-16世紀民衆本に見る、魔術師の変身と古代自然観の関係について」
溝井裕一
日本昔話学会 2005年7月
「魔術師ファウストと変身のモティーフ-『魔術』に隠れた古代の自然観について」
溝井裕一
グリムと民間伝承研究会 2005年5月
「魔術師ファウストの復活-ファウスト民衆本や伝説にみられる、『死と再生』のモチーフについて」
溝井裕一
阪神ドイツ文学会 2005年4月
「『魔女』に対する拷問と処刑」 (シンポジウム《グリム・メルヒェンと「魔女」》)
溝井裕一
関西大学独逸文学会 2004年9月
サントリー学芸賞(社会・風俗)
2018年12月 サントリー文化財団
ケルンの彫刻家パレンベルクの古生物復元模型と「植民地時代の古生物学」
研究課題/領域番号:23K00450 2023年4月 - 2026年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
溝井 裕一
配分額:3900000円 ( 直接経費:3000000円 、 間接経費:900000円 )
水族館文化-「水中世界」を表象する施設の研究
研究課題/領域番号:16K16756 2016年4月 - 2019年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(B)
溝井 裕一
配分額:2860000円 ( 直接経費:2200000円 、 間接経費:660000円 )
研究代表者はもっぱら、近代水族館がヨーロッパで誕生し、それがアメリカ、日本へとわたったあと、社会や時代の要請に応じていかに変化していったかを追及した。具体的には、水族館は元来あくまでも水生生物を見せるための場であったが、しだいに没入感を楽しむ場、あるいは植民地支配を表象する場となり、さらに戦後は水中撮影技術の発達や動物の権利運動などの影響を受けて、展示スタイルを変えていったプロセスを、グローバルな視点から明らかにした。これと並行して、古代~近世における日欧の水族「観」や海洋「観」の研究もおこなった。
想起する帝国―ナチス・ドイツにおいて想起された「過去」の研究
研究課題/領域番号:25370388 2013年4月 - 2016年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
溝井 裕一, 細川 裕史, 齊藤 公輔, 浜本 隆志, 森 貴史, 北川 千香子
配分額:3770000円 ( 直接経費:2900000円 、 間接経費:870000円 )
我々は、ナチスによる集合的記憶の乱用の問題について調査を実施した。その結果、ナチスが過去の「アーリア人の遺産」に由来する要素を、建築、祝祭、演説などに織り込み、これによってドイツ人のアイデンティティを変化させ、彼らに人種主義的かつ優生学的な思想を植え付けようとしたことが明らかとなった。ナチスが実施した絶滅動物の復元も、「過去の想起」に関連するものであった。
我々はまた、戦後の大衆文化における「集合的記憶におけるナチスのイメージ」も研究対象とした。そして、ナチスのイメージは現実というよりも我々の期待を反映したものにすぎず、世代交代や社会環境の変化に合わせて変質していくものであることを解明した。
グリム童話を中心とするドイツ伝承文学におけるジェンダー
研究課題/領域番号:24520379 2012年4月 - 2015年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
野口 芳子, 溝井 裕一, 山本 まり子, 大野 寿子, 竹原 威滋, ベルンハルト ラウアー, 金城ハウプトマン 朱美, 大野 寿子
配分額:5070000円 ( 直接経費:3900000円 、 間接経費:1170000円 )
グリム童話出版200年祭、日本ジェンダー学会大会、日本独文学会大会などでシンポジウムを開催し、グリム童話やドイツ伝説集における父親像、母親像、家族像を浮き彫りにした。その成果を9本の学術論文や3冊の著書にして出版した。
ドイツ・カッセルのグリム兄弟協会大会で招待講演を行い、リトアニア国ヴィリニュス大学の国際口承文芸学会で発表した。発表は評価され、国際的学会誌「Fabula」56号への掲載が確約された。日本におけるグリム童話受容は英訳からの重訳により、ビクトリア朝英国のジェンダー観や道徳観の影響を受けていたことを立証した。明治期日本の西洋化は技術だけでなく、道徳にも及んでいたのだ
超域する「異界」-異文化研究・国語教育・エコロジー教育の架け橋として-
研究課題/領域番号:21520383 2009年 - 2011年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
大野 寿子, 石田 仁志, 河地 修, 木村 一, 千艘 秋男, 高橋 吉文, 竹原 威滋, 中山 尚夫, 野呂 香, 溝井 裕一, 山田 山田, 山本 まり子, 渡辺 学, 早川 芳枝, 藤澤 紫, 池原 陽斉, 松岡 芳恵
配分額:4420000円 ( 直接経費:3400000円 、 間接経費:1020000円 )
「異界」を、「死後世界」および「時間的空間的に異なった領域」をも指し示す、古来より現代に至る人間の精神生活の「影」、「裏」、「奥」に存在しうる空間領域と定義し、その射程をクロスジャンル的に比較考察した。文字テクストのみならず、音楽・図像における「異界」表現、精神生活内の「異空間」としての「異界」、仮想空間、コミュニケーション上の他者としての「異界」等、「異界」という語と定義の広がりとその広義の「異界」に潜む、何でも「異界」にしてしまう現代日本語の危険性を考察した
伝説・民衆本におけるファウスト像と16世紀の世界観
研究課題/領域番号:07J03800 2007年 - 2008年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費
溝井 裕一
配分額:1000000円 ( 直接経費:1000000円 )
今年度において研究代表者は、「ファウスト伝説」が育まれた背景にある16世紀ドイツの魔法信仰、悪魔信仰の研究を進めるとともに、集合的記憶研究と伝説研究の接点について考察を行なった。まず、今年度の全期間をかけて著書『ファウスト伝説』を執筆した。そこでは従来の研究成果に加えて、8月3日〜9月日にヨーロッパで収集した資料を参照しながら近世の世界観についてより詳細に論じている。また近世の魔法信仰を知る上で貴重な資料である『魔法に関するキリスト教的考察と警告』(アウグスティン・レルヒアイマー、本名ヘルマン・ヴィテキント、1586年)の内容を分析し、その成果を2008年6月14日、日本独文学会で発表している。さらにこれとは異なるアプローチとして、論文「伝説と集合的記憶」を書き、伝説研究と集合的記憶研究の接点について論じた。集合的記憶とは、個人だけでなく集団においても過去のイメージの再構築がおこなわれると想定して用いられる概念である。記憶研究によれば、集団や個人が過去を想起する時、過去にまつわる情報の選択と結合が行なわれる。その際、想起する者の欲求に従って、過去のイメージが歪められたり、新たに架空の要素が混入したりすることがある。研究代表者は、この過程と伝説形成の過程に類似点があることに着目した。伝説が形成される場合も、担い手の欲求に従って歴史的事件や人物に関する過去の情報が選択され、それらが古い物語の展開にあわせて結合される。しかもこの時、史実とはかなり異なる過去像がしばしば提示されるのである。研究代表者は本論文の中で、伝説形成を集合的記憶における想起のプロセスのひとつと位置づけて考察した。
現時点では、パワーポイントとレジュメを連携させた授業をおこなっている。これにより、学生は異文化について視覚的に学ぶことが可能となり、モチベーションの向上をもたらすことができる。またレジュメはWebを通じてダウンロード可能となっている。いくつかの講義では、授業の最後に教えたことを書かせるようにした。これにより、学生は授業内容を復習することができる。ゼミにおいては、学生の発表ののち、各テーマに関するレジュメを改めて配布し、概要を述べるスタイルをとったが、これが学生には好評であった。またアンケートを実施した際は、質問や要望にたいし、できるだけレスポンスするよう心がけた。オフィスアワーでは、発表等で行き詰った学生や、将来について相談のある学生が来ると、真摯に対応している。
自分で作成したレジュメを主に活用している。これは講義に関係する図版、キーワード、メモ欄を配したものであり、復習等に活用できる。リレー講義「ヨーロッパのマイノリティ」や「ジェンダー文化論」などでは教科書を使用し、これとレジュメを組み合わせて授業をおこない、ドイツ語の授業では指定教科書を使用した。
特になし。
特になし。