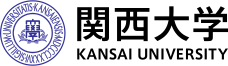学位
-
修士 ( 1996年3月 筑波大学 )
研究分野
-
人文・社会 / 教育学
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
グローバル化時代における各国公立学校の外国籍教員任用の類型とその背景に関する研究
研究課題/領域番号:15K04326 2015年4月 - 2019年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
広瀬 義徳, 棚田 洋平, 金 侖貞, 榎井 縁, 権 瞳, 中島 智子, 李 月順, 呉 永縞, 金 相文, 藤川 正夫, たて なほこ, 薮田 直子
配分額:4550000円 ( 直接経費:3500000円 、 間接経費:1050000円 )
第一に、グローバル化時代における外国籍教員の任用・雇用の状況・背景を解明する目的や意義、先行研究の知見や課題等を明確にした。第二に、1991年の文部省通知に至る日韓での官民の動きを多様なアクターに関する資料から跡付け、その来歴と経緯を解明した。第三に、1970年代初頭からの日本各地での外国籍教員の任用をめぐる動きを詳細に叙述した。第四に、諸外国における公立学校の外国籍教員の任用・雇用に関する調査から、3つの類型を見出した。第五に、諸外国における外国籍教員の任用・雇用類型をふまえて、国際的な文脈の中で日本の任用方針を位置づけ、今後選択可能な政策・制度のシナリオを5点に絞って描出した。
-
公立学校における外国籍教員の実態と課題の解明
研究課題/領域番号:24653256 2012年4月 - 2014年3月
日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究
中島 智子, 金 侖貞, 広瀬 義徳
配分額:2340000円 ( 直接経費:1800000円 、 間接経費:540000円 )
本研究は、3つの方法によって公立学校に任用されている外国籍教員の実態と課題の解明を行った。まず、都道府県政令指定都市教育委員会宛の郵送調査及び一部教委への訪問調査の結果、全国に257人が任用されていること、任用方式と給与等級に多様性があることが判明した。次に、12自治体の外国籍教員(一部日本国籍取得を含む)に聞き取り調査を行った結果、教員志望の契機や任用までの状況、他の教職員や子ども、保護者との関係で世代による違いが見られるが、全体として外国籍教員の存在やその職について日本社会や学校内で十分に理解が及んでいないことが明らかになった。最後に、外国籍教員に関する日本政府の対応等を整理分析した。
-
戦後日本の教員処分をめぐる総合的研究(2)-教育公務員の分限処分を中心にして
研究課題/領域番号:21530860 2009年 - 2011年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
元井 一郎, 尾崎 公子, 住友 剛, 広瀬 義徳
配分額:2600000円 ( 直接経費:2000000円 、 間接経費:600000円 )
本研究は、1951年の講和条約発効以降の教員処分に関する政治社会構造の観点から分析検討を行なったものである。研究の過程において、私たちは当該時期を、1956年を画期として前半期と後半期に区分した。画期を1956年に設定したのは、後述するように「地教行法」(地方教育行政のための組織運営に関する法律)の制定を機軸とする戦後地方教育行政制度の変容と新たな構造構築の基点であると考えたからである。
前半期は、占領政策終結後の教員処分の構成を当時の政治経済構造との関連において検討を行った。周知のようにこの時期は、東西冷戦を背景に政治的な教員処分が実施されている。こうした動向は、占領期における処分構造と同様であり、主要な処分手法として教員公務員の分限処分が多用されていた。こうした構造の史的展開を通じて、戦後の行政組織は、戦前的な組織の再編を実行し新たな組織編成を行ったのである。まさに、地教行法は、新たな地方教育行政の組織実態を反映する法的な画期だと指摘できる。もう少し行政組織内的な編制で敷衍すれば、戦前の内務行政とそれを掌握する内務省的な教育行政、とりわけ教員支配を、内務省解体後の新たな行政組織の中で確立したことを意味するのである。指摘するまでもなく、内務省的な支配編制は、単に強権的支配だけでなく、経済財政構造に立脚する効率的な支配構造をも意味する。まさに1956年は、こうした内務省的支配の構造が、より経済財政構造と、換言すれば大蔵省的な財政配分を機軸に中心を異動させる画期であると指摘できる。したがって、本研究における歴史区分としての後半期は、そうした財政構造を機軸とした新たな教員の支配構造を、そして教員処分を実行した時期といえるだろう。こうした地方教育行政の変容を例示する事件として、佐賀県教組事件を挙げることができるだろう。本研究の視点からいえば、1956年の「地教行法」(地方教育行政のための組織運営に関する法律)の制定から1958年「標準定数法」(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律)制定に至る過程、つまり戦後教員処分体制が地方教育行政の中心である教育委員会を基軸に新たな体制を構築する過程に重複するものである。その意味で、佐賀県における県財政逼迫にともなう教員馘首あるいは給与削減という教員処分の実施過程は、その実施における行政的政治的背景が大きく作用する。その後、勤務評定政策の実施の前段となる佐賀県の教員処分に係る実施体制は、偶発的に構築されたものではない。少なくとも、県教委教育長人事などを概観すれば、文部省を中心とする地方教育行政体制の構築という政策意思が概観できる。今回の研究期間で実施した、高知県の勤評闘争に係るインタビューや佐賀事件の当事者へのインタビューを通して大きな史実調査における成果を得た。さらに言えば、こうした教員処分体制の構築は、戦前の内務省が支配・所管していた地方教育行政を文部省が肩代わりする体制への転換に係って実行されたと指摘できる。こうした点は、他の都道府県における教員勤務評定をめぐっての闘争に関する調査を実施し、改めて立体的な検討が必要であることが課題として明瞭となったと指摘しておきたい。 -
東アジアにおける戦争・植民地記憶の保存と表象に関する国際的総合研究
研究課題/領域番号:18320097 2006年 - 2009年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
君塚 仁彦, 又吉 盛清, 王 智新, 趙 軍, 渡辺 雅之, 石 純姫, 橋本 栄一, 大森 直樹, 近藤 健一郎, 広瀬 義徳, 王 智新, 又吉 盛清, 趙 軍, 蘇 林, 石 純姫
配分額:19420000円 ( 直接経費:16000000円 、 間接経費:3420000円 )
本研究では、中国・台湾・韓国・ロシア(サハリン地域)・日本など東アジアを対象として、19世紀末から20世紀にかけての戦争と植民地統治をめぐる記憶がどのように収集・保存され、公開・表象されてきたのかを、ヨーロッパとの比較も含め調査研究した。東アジアにおける戦争・植民地記憶の保存と表象は、各国各地域相互の歴史認識の差異や政治状況を背景として、欧州とも異なる複雑多岐な様相を呈している。同時に、戦争や植民地支配への抑圧と抵抗の記憶、平和追求のためのモニュメントとして、東アジアにおける歴史認識の分断ではなく連帯のあり方を模索する上で重要な意義を有するものであることが明らかにされた。
-
日本の植民地教育実態に関する総合的国際共同研究
研究課題/領域番号:16330156 2004年 - 2006年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B)
王 智新, 大森 直樹, 藤澤 健一, 広瀬 義徳, 趙 軍, 蘇 林, 石 純姫
配分額:15000000円 ( 直接経費:15000000円 )
かって日本の遂行した植民地教育の全貌解明を目的とした本研究は三年間経過し、研究をさらに掘り下げて下記のような調査を進めてきた。植民地教育についての研究は、何よりも史料先行である。いままでは、共同研究と称して、日本の学者が中国や韓国に出かけていって、そこら辺にある資料を、手段を選ばずに手に入れて持って帰り、それを元に論文を書いたり、資料集を出版したりした、と旧植民地国々の学者から非難が上がっている。そのような旧来のパターンを打破し、新しい協力体制が求められている。一見、華やいだ植民地研究の裏には、実は旧植民地主義者と通底する発想がある。決して理想とはいえない今日の研究状況を改善するためには、中国や韓国など旧植民地国家の学者とともに協力して研究に取り組むべきであると痛感した。そして、何らかの協力システムの構築を試みようと実践した。そのような構想、あるいは実践は、今度の科研費による一連の研究の目標となる。本研究は、モノ(記念碑ほか)、事件(教員弾圧事件ほか)、ヒト(人物への聞き取りほか)を軸に、学術史調査と資料調査を中心に展開してきた。無論、それは画一的ではなく、それぞれが自分の研究ベースに合わせて実施していった。そして、われわれは、理論的思索と実践的な考察との結合、学術史調査と資料調査との結合、フィールドワークをしながら思考の深化を目指すという認識を韓国・中国ならびにその他の旧植民地国家と地域の学者と共通した。さらに、課題の「植民地教育実態研究」については、学校教育に限定するのでなく、社会教育、職業教育、書道、音楽、言語など人間形成の社会的な過程という広い意味での教育という理解を元に、植民地における文化・教育を通じた、人間の支配・統制の問題について多元的で立体的にその全貌の解明を努めてきた。今回の研究の成果も韓国と中国の学者と分かち合った。
-
日本の植民地教育実態に関する国際共同研究企画
研究課題/領域番号:15633008 2003年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
王 智新, 藤澤 健一, 石 純姫, 広瀬 義徳, 大森 直樹, 蘇 林
配分額:2900000円 ( 直接経費:2900000円 )
従来のこのテーマについての研究は、教育政策・制度史、あるいは日本人教員史や教科書統制といった、民地支配を行った側の視点から実態分析を行ってきたといわれ、占領下・植民地教育の全貌を反映するには至らなかった。それは受けた側には、実施側と同等、あるいはそれに相当する資料が欠如していることに由来する。日本の植民地教育の実態分析を深める事を目的として、本企画では以下の作業を通じて、中国、韓国その他の国々の研究者との信頼関係を醸成しつつ、彼らの協力を得た国際共同研究及び調査実施をして、従来の研究の弱点の克服を試みた。
第一に、(1)植民地教育の実態的側面を分析するために、各種史料の所在とその内容の調査。そのために、遼寧省歴史文書史料保存館、上海市図書館をはじめとする主要な史料保存先、学説史に関する基礎的調査のために、黒龍江省社会科学院、ハルピン工業大学、吉林省歴史文書史料保存館、東北大学、北京大学、中国社会科学院日本研究所、沈陽師範大学、天津市社会科学院、南開大学、復旦大学など主要な研究機関を訪問し、学説史に関する基礎的調査をし、意見交換をした。
さらに、福岡と上海において、中国・日本及び韓国の研究者と研究調整会議を実施し、研究について打ち合わせ、調整を行った。
(2)上記の研究を進めるなか、特に植民地支配を受けた側からみた、植民地教育の実態に関する学説史についての予備的調査。未邦訳及び日本での紹介が未だなされていない史料・文献・論文及び体験者の回想・オーラル・ヒストリーなどを中心にして、学校教育関連だけではなく、教育文化的な視点をもつ素材を視野に収めつつ、その体系的な収集・整理を行ってきた。
第二に、第一の成果を踏まえ、今後の国際共同研究の方向性を明確にしていくための意見交換と成果発表のため、2003年12月、中国・重慶(西南師範大学)において、開催される第六回植民地教育研究国際シンポに参加し、韓国、アメリカ、台湾・香港、マカオを含む中国の研究者及び体験者と意見交換を通じて、本企画調査の成果と課題を総括しながら、本研究の到達点と克服しなければならぬ問題点を課題として明らかにし、今後の国際共同研究の基盤を固め、展開する企画をした。
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)
-
2009年度、2011年度担当している「知へのパスポート」の授業では、参加型授業として学生のグループワークやパワーポイントを利用したプレゼンテーションの方法習得などを組み込んで授業運営した。 2011年度担当した「知のナヴィゲーション」では、少人数制を活かして、スチューデントスキル全般の入門的な教授を目指し、論文などのリーディングの方法、レポートのライティングスキル、議論の方法習得などを中心に、学生主体の演習形式による授業を行っている。また、両授業では、文学部GPに基づく卒論ラボの協力を得ながら、授業外での添削指導も行った(2010年より卒論GPの卒論ラボ委員を担当)。 2009年度より毎年「教育制度論」については、150~250名という大教室のため、学生からの授業評価による要望を受け止め、毎回事前に講義で利用するパワーポイント資料を事前にインフォメーションシステムにUPし、学生の予習と復習に資するよう配慮している。 ゼミでは、毎年、教育文化専修で秋期に実施されるインターゼミ合宿に向けた共同学習として、課題図書の読解と資料検索、個人発表、全体討議などを重ね、学生間の対話による学び合いを重視している。
作成した教科書、教材、参考書
-
最近過去5年間に作成したテキストは、下記の通りである。 第一点目は、菱田隆昭編著『幼児教育の原理』(株みらい、2006年5月)。概要を述べれば、保育所、幼稚園に関連した評価の基本的な意味、方法、種類を概説し、保育における自己評価から第三者評価までの必要性と要点を理解できるようにした(広瀬義徳「第10章 自己評価から第三者評価まで」を分担執筆)。 第二点目は、岡田裕編著『最新保育テキストブック3 教育原理』(聖公会出版、2009年)、概要を述べれば、各国の教育制度の特徴やその構成原理といった基本的な知識の解説からはじまり、現代日本における幼児教育及び初等教育の制度的側面を概説するとともに、新学習指導要領を含めたカリキュラムの特徴と問題点が理解できるように叙述した(広瀬義徳「第4章 教育制度」を分担執筆)。
教育方法・教育実践に関する発表、講演等
-
教職専門科目担当者として2008年度より毎年参加している関西大学教職専門科目担当者研究会にて、2010年3月13日、大学における教員養成の課題について基調報告を行った。報告の概要は、「団塊の世代」の大量退職時代を迎えた今日、近年の学校組織や教員採用に起きている状況変化を踏まえ、大学における教員養成においてどのような改革・対応が求められているのか、その課題について整理し、また、若干の論点を提示するものであった。また、関西大学教職支援センター委員として、同センター設立の趣旨と事業概要について簡単な紹介も行った。当日は、大阪府教育委員会より講師を招聘し、有意義な討議の時間となった。
その他教育活動上特記すべき事項
-
2008年は免許資格部門委員会委員、2009年より関西大学の教職支援センター委員、2010年より教職科目検討プロジェクト委員、2009年より教員免許更新講習必修領域とりまとめ及び教員免許更新講習「教育政策の最新動向を理解する」講師などを担当し、関西大学の教職課程に関する業務に広く従事している。また、2010年より阪神地区私立大学教職課程研究連絡協議会の幹事校会員、2011年10月より教職支援センター副センター長に任ぜられている。 2009年より高大連携事業の一環として、KanDai15セミナーで科目「学びの扉」への高校生の受け入れ指導、高校への出張講義、大学での模擬授業などを複数担当している。 吹田市民大学公開講座に、2008年及び2009年は講師として、2011年度は企画責任者として関わった。教育文化専修が企画する本講座では、毎回、現在的な課題・テーマを取り上げ、地域の成人・社会教育に貢献している。 2008年度から2010年度まで、福島県内、大阪府内の教職員団体の研修会・セミナー・フォーラムなどにおいて複数回講演した。