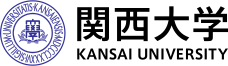研究キーワード
-
操作説明
-
ESDA
-
ディスコ-ス分析
-
プロトコル分析
-
ビデオプロトコル分析
-
小学生
-
能力
-
教師
-
フィールドワーク
-
思考スタイル
-
大学生
-
相互行為
-
社会的構成
-
児童
-
教室
-
知能
-
性格
研究分野
-
人文・社会 / 認知科学
経歴
-
関西大学 文学部 助教授
2001年 - 2002年
-
静岡大学 情報学部 講師
1997年 - 1998年
共同研究・競争的資金等の研究課題
-
教室内における認知的個人差の社会的構成過程とその変容に関する研究
研究課題/領域番号:13610174 2001年 - 2002年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
松村 暢隆, 比留間 太白
配分額:2500000円 ( 直接経費:2500000円 )
本研究は、能力に代表される認知的個人差が学校教育現場、その中でも特に、教室内における教授学習場面において、どのように構成されていくのか、その社会的構成過程を明らかにするとともに、R.J.スタンバーグによる「思考スタイル」という新しい個人差を捉える概念を教師を通して教室に導入する際、どのような変容が生じる可能性があるのかを、教授学習過程の詳細な分析と、教師への質問紙の実施インタビューを通して把握することを目的とした。
(1)まず、知能研究における思考スタイルの理論的位置の検討をおこなった。思考スタイルは、知能(認知)と性格との接点と位置づけられ、R.J.スタンバーグによる知能の三部理論における心的な自己管理の特殊形態とされている。彼の知能理論における三種の知能との関連性はみられるが、完全に一致しているわけではないことが示された。
(2)次に、道具としての各種思考スタイル質問紙日本語版の開発をおこなった。簡易版、学生用自己評定質問紙、教師用思考スタイル質問紙を作成し、その評価をおこなった。
(3)実際の教授学習場面における能力概念の利用とその構成過程を検討するため、小学校低学年1学級を月1回1日の観察を5ヶ月間おこなった。併せて、教師へのインタビュー、教師自身の思考スタイル調査と児童の思考スタイル評価をおこなった。延べ900分にわたる教室内の会話データから詳細なトランスクリプトが作成された。教師自身に実施した思考スタイル質問紙の結果、教師による児童の評価、インタビューにおいて表現された教師の児童観、教授学習場面において観察される児童観との間には、一致する点もみられたが、他方で、不一致の点があることがみいだされた。
今後の課題として、道具としての思考スタイル可視化方法の開発と、これを用いた縦断的な介入研究が可能となるような教育実践プログラムの検討・開発があげられる。 -
操作説明のデジタルビデオプロトコル分析手法の開発と評価
研究課題/領域番号:09710084 1997年 - 1998年
日本学術振興会 科学研究費助成事業 奨励研究(A)
比留間 太白
配分額:2100000円 ( 直接経費:2100000円 )
本研究は、映像のデジタル化技術を応用した操作説明の新しい分析技術(デジタルビデオプロトコル分析手法)を開発し、さらに、分析技術を具体的な課題に適用し、その評価を行うことを目的した。
本年度の研究成果は以下の通りである。
昨年度および本年度に作成したビデオコーパスの分析および、本ツールを利用する場面の分析を通して作成したプロトタイプの評価を行った。
作成された分析ツールのプロトタイプは、映像データのクリップをボタンとして配置し、これを押すと当該のクリップが再生されるようになっているものである。分析においては、このボタンをKJ法的に利用して、カテゴリーの作成を支援することになる。
評価の結果、会話などの音声データの分析に対しては、有用な方法であることがわかった。また、データをアクセス速度がハードディスクより劣るCD-R、DVD-RAMに保存した場合も、十分分析に耐えることがわかった。ただし、いくつかの改善すべき点があることも判明した。
1: 分析の際には、正確な時刻・フレームをオンタイムで表示することが必要である。
2: 動作等を分析するためには、画像のサイズを少なくとも320×240ピクセル以上にする必要がある。
3: 相互作用の動作分析、とくにコンピュータなどの人工物を利用した相互作用の場合には、相互作用と、人工物の挙動を記録する2台以上のカメラが必要であり、2つの映像を同期させ、分析することが可能なツールが必要である。
4: クリップした画像それぞれに言語によるタグ付けを行う必要がある。
今後開発したツールを公開するとともに、マルチプラットホームに対応させる予定である。
教育内容・方法の工夫(授業評価等を含む)
-
週1コマ分をオフィス・アワーとして、学生からの質問や相談に応じている(2006~2011年度) 授業用、ゼミ用のtwitterアカウントを設定し、授業において話題とできなかった内容や学生からの質問への応答、心理学の最新研究内容について随時配信している(2010~2011年度) ゲストスピーカーとして企業で活躍している方を招き、認知心理学に関する講義内容が企業現場でどのように活用されているか講演していただき、学問と企業活動との関連を実感できるようにしている(2008~2011年度) ゼミ3回生13名にインターネットに常時接続可能なタブレットPCを持たせて、研究データの収集や共有をユビキタスにできる環境を整えたゼミ運営を試みている(2011年度)
作成した教科書、教材、参考書
-
認知心理学a(学部) 比留間太白・山本博樹(編著)『説明の心理学』ナカニシヤ出版 2007年 心理学専修ゼミ1,2 (学部)海保博之・大野木裕明・岡市広成(編著)『新訂 心理学研究法』放送大学教育振興会 2008年(分担執筆)
教育方法・教育実践に関する発表、講演等
-
特になし
その他教育活動上特記すべき事項
-
高大連携を推進するために設けられた、kandai1セミナーに担当者として登録し、年1~2回程度、依頼のある高校において、出張講義を行っている(2006~2011年度)